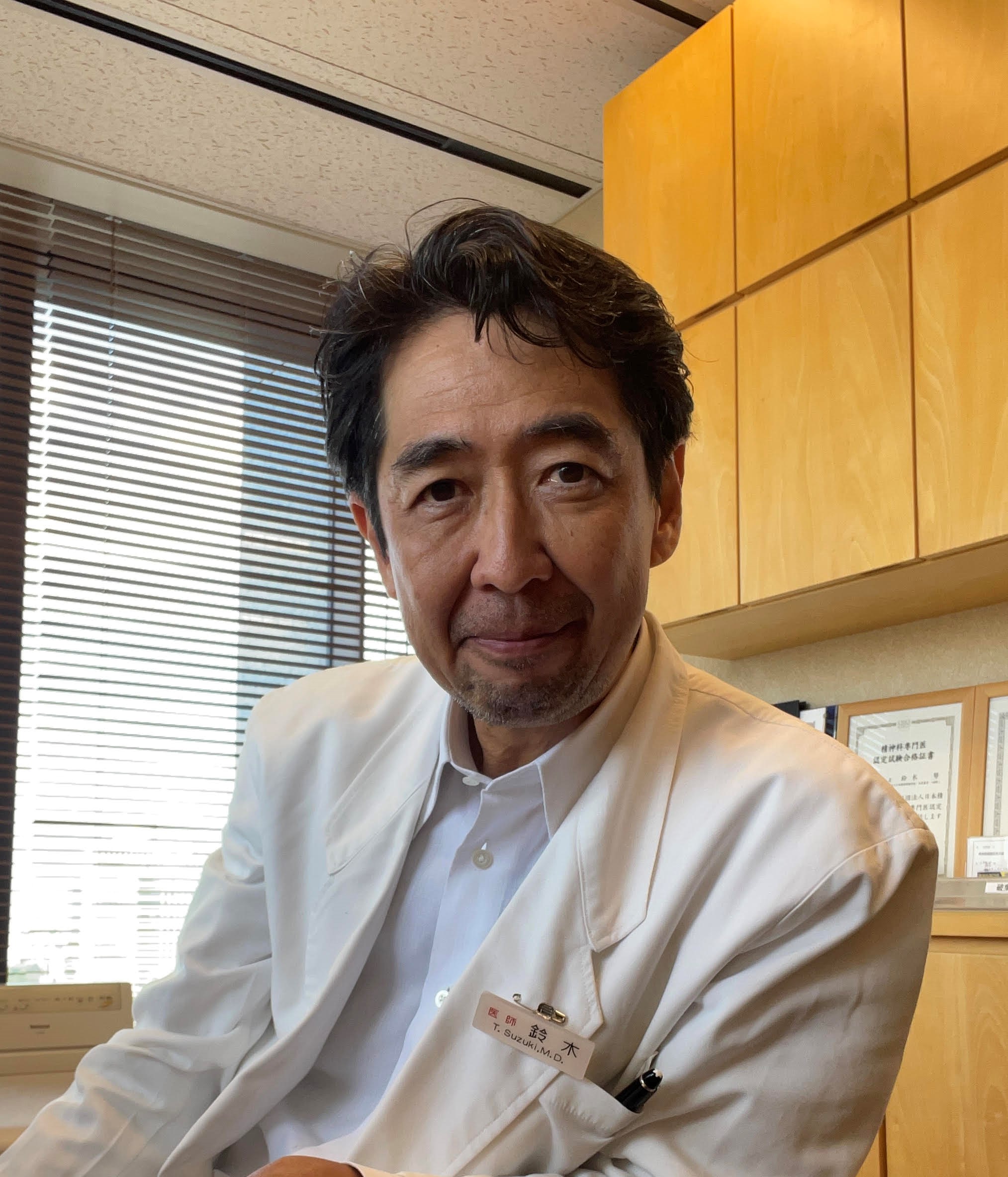その36 パワハラ防止法 (対話の重要性)
2022年4月から、パワハラ防止法が中小企業に於いても施行されます。
パワハラ防止法とは、改正労働施策総合推進法の通称です。 パワーハラスメント防止のための雇用管理上の措置が、企業にはじめて義務付けられました。大企業では2020年6月から施行されています。
企業における職場におけるパワハラ防止措置として
1.事業主の方針を周知・啓発
2.相談体制の整備
3.迅速で適切な事後対応
4.その他
となっています。
パワハラ指針では、職場におけるパワハラは、以下のように定義されています。
職場において行われる
①優越的な関係を背景とした言動であって、
②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、
③労働者の就業環境が害されるものであり、
①から③までの要素を全て満たすもの(セクハラと異なり、客観性が求められます)
代表的な言動の類型として、6つの類型が例として示されています。
(1)身体的な攻撃 暴行や障害など
(2)精神的な攻撃 人格を否定するような言動、名誉毀損や侮辱、暴言など
(3)人間関係からの切り離し 仲間外しや無視など、職場での孤立を招くもの
(4)過大な要求 業務上不要なことや不可能なことの強制など
(5)過少な要求 程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと
(6)個の侵害 私的なことに過度に立ち入ること
厚生労働省「あかるい職場応援団」実施の調査データ(平成28年)によると、過去3年間に、実際にパワーハラスメントに関する相談を1件以上受けたことがある企業は回答企業全体の49.8%で、その8割がパワハラに該当するものでした。
今回特筆すべきことは、パワハラに起因する精神障害の労災認定基準も明確化された、点です。パワハラは精神的なストレスをもたらします。パワハラ防止法の改正においてパワハラの定義が明確化されたことを受けて、パワハラに関連する精神障害に関する労災認定基準も明確化されました。
具体的には、労災認定基準の要件の一つである「業務による心理的負荷」について評価表の中に「パワーハラスメント」という項目が新設されました。これにより、パワハラに起因する精神障害について、労災の認定判断がしやすくなりました。
昨年12月「部下を褒めない、叱らない、命じない。ー新しいリーダー論」が上梓されました。アドラー心理学の岸見一郎先生が執筆しています。要約しますと、
以下抜粋ーーー
リーダーと部下(メンバー)は対等である。
リーダーは次の3つの原則を守らなくてはならないと「先生」は主張します。
◎ 叱ってはいけない
◎ ほめてはいけない
◎ 命令してはいけない
わたしは叱ることは必要でないと考えています。改善を求めなければならないことがあれば、言葉で伝えればいいのです。それも即効性を求めてはいけません。手間暇をかけていわないといけません。緊急を要することであったら止めないといけませんが、それですら言葉を使えばいいのであって、感情的になる必要はありません。
ーーー抜粋終わり。
褒めない、叱らない、命じない、ならどうするか。対話することが大切です。対話とは、会話の中でも特に共通の目的意識を持つものを指します。会社での対話は、会社をよくしようという共通の目的を持つことが特徴です。
対話するには、意見が異なったとしても相手を尊重し、価値観をより深く理解するために質問をし、建設的な発言を積み重ねることが重要です。
ITC技術の発展によって世代間に価値観の相違が生まれ、対話にすれ違いが生じることが多くなっています。
生まれた年代別に
X世代(現代社会の中心 1965-80年頃の生まれ 42-57才) 高度成長、テレビ、電話、年功序列、努力、
Y世代(ミレニアル世代 1980-95年頃の生まれ 27-41才)、氷河期、インターネット、メール、ゆとり、
Z世代(デジタルネイティブ世代 1996年以降の生まれ 26才以下)スマホ、チャット、多様性、
などと分類されます。常識とされる知識や社会情勢は常に変化していくということです。
ちなみに私などX世代の前はベビーブーム世代(1945-1964)というそうです。
対話をする上で大切なことは、お互いの価値観を尊重し、意見が異なる時は質問を繰り返し、時間をかけて目的に到達させることです。これらの価値観の相違を理解していないと、良かれと思って教えたことがパワハラになるかもしれません。
X世代「受話器は静かに置きなさい」
Z世代「受話器って何ですか?」
以上です。
(参考文献)
明るい職場の応援団(厚労省)
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/
叱らない、褒めない、命じない。新しいリーダー論
2021年12月 岸見一郎著
“GENERATION X”
1951年 Robert Capa
パワハラ防止法とは、改正労働施策総合推進法の通称です。 パワーハラスメント防止のための雇用管理上の措置が、企業にはじめて義務付けられました。大企業では2020年6月から施行されています。
企業における職場におけるパワハラ防止措置として
1.事業主の方針を周知・啓発
2.相談体制の整備
3.迅速で適切な事後対応
4.その他
となっています。
パワハラ指針では、職場におけるパワハラは、以下のように定義されています。
職場において行われる
①優越的な関係を背景とした言動であって、
②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、
③労働者の就業環境が害されるものであり、
①から③までの要素を全て満たすもの(セクハラと異なり、客観性が求められます)
代表的な言動の類型として、6つの類型が例として示されています。
(1)身体的な攻撃 暴行や障害など
(2)精神的な攻撃 人格を否定するような言動、名誉毀損や侮辱、暴言など
(3)人間関係からの切り離し 仲間外しや無視など、職場での孤立を招くもの
(4)過大な要求 業務上不要なことや不可能なことの強制など
(5)過少な要求 程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと
(6)個の侵害 私的なことに過度に立ち入ること
厚生労働省「あかるい職場応援団」実施の調査データ(平成28年)によると、過去3年間に、実際にパワーハラスメントに関する相談を1件以上受けたことがある企業は回答企業全体の49.8%で、その8割がパワハラに該当するものでした。
今回特筆すべきことは、パワハラに起因する精神障害の労災認定基準も明確化された、点です。パワハラは精神的なストレスをもたらします。パワハラ防止法の改正においてパワハラの定義が明確化されたことを受けて、パワハラに関連する精神障害に関する労災認定基準も明確化されました。
具体的には、労災認定基準の要件の一つである「業務による心理的負荷」について評価表の中に「パワーハラスメント」という項目が新設されました。これにより、パワハラに起因する精神障害について、労災の認定判断がしやすくなりました。
昨年12月「部下を褒めない、叱らない、命じない。ー新しいリーダー論」が上梓されました。アドラー心理学の岸見一郎先生が執筆しています。要約しますと、
以下抜粋ーーー
リーダーと部下(メンバー)は対等である。
リーダーは次の3つの原則を守らなくてはならないと「先生」は主張します。
◎ 叱ってはいけない
◎ ほめてはいけない
◎ 命令してはいけない
わたしは叱ることは必要でないと考えています。改善を求めなければならないことがあれば、言葉で伝えればいいのです。それも即効性を求めてはいけません。手間暇をかけていわないといけません。緊急を要することであったら止めないといけませんが、それですら言葉を使えばいいのであって、感情的になる必要はありません。
ーーー抜粋終わり。
褒めない、叱らない、命じない、ならどうするか。対話することが大切です。対話とは、会話の中でも特に共通の目的意識を持つものを指します。会社での対話は、会社をよくしようという共通の目的を持つことが特徴です。
対話するには、意見が異なったとしても相手を尊重し、価値観をより深く理解するために質問をし、建設的な発言を積み重ねることが重要です。
ITC技術の発展によって世代間に価値観の相違が生まれ、対話にすれ違いが生じることが多くなっています。
生まれた年代別に
X世代(現代社会の中心 1965-80年頃の生まれ 42-57才) 高度成長、テレビ、電話、年功序列、努力、
Y世代(ミレニアル世代 1980-95年頃の生まれ 27-41才)、氷河期、インターネット、メール、ゆとり、
Z世代(デジタルネイティブ世代 1996年以降の生まれ 26才以下)スマホ、チャット、多様性、
などと分類されます。常識とされる知識や社会情勢は常に変化していくということです。
ちなみに私などX世代の前はベビーブーム世代(1945-1964)というそうです。
対話をする上で大切なことは、お互いの価値観を尊重し、意見が異なる時は質問を繰り返し、時間をかけて目的に到達させることです。これらの価値観の相違を理解していないと、良かれと思って教えたことがパワハラになるかもしれません。
X世代「受話器は静かに置きなさい」
Z世代「受話器って何ですか?」
以上です。
(参考文献)
明るい職場の応援団(厚労省)
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/
叱らない、褒めない、命じない。新しいリーダー論
2021年12月 岸見一郎著
“GENERATION X”
1951年 Robert Capa
その35 花粉症時期の点眼薬の使い方(あくびのすすめ)
今週から急に暖かくなっています。今年の2月の気温は、平年と比べて1.2度低かったそうですので、喜びはひとしおです。反対に気になるのが花粉症です。
2022年の花粉飛散量は例年の1.2倍でやや多いようですが、皆さんマスクをきちんとつけているので、喉と鼻の症状は少なく、目の症状を強く感じるようです。
今回のテーマは、花粉症の点眼薬の使い方です。
市販の点眼薬を見てみると、アレルカット(第一三共 738円)、アルガード(ロート 1436円)、アルピタット(武田 938円)となっています。これらの点眼薬の主成分は、クロモグリク酸ナトリウム(インタール、医薬品登録中止、抗アレルギー薬、1972年発売)、クロルフェニラミンマレイン酸塩(ポララミン、抗ヒスタミン薬、1953年発売)です。
ポララミンは第一世代抗ヒスタミン薬と呼ばれ、私が研修医(1990年代初頭)の頃には「口渇、便秘、眠気の副作用に注意すること」と言われていました。1994年に眠気の少ない、いわゆる第二世代と呼ばれるアレジオンが発売されてからは、第一世代は医療機関ではほとんど使用されず、副作用の眠気を利用して、市販の睡眠薬(正しくは睡眠改善薬、商品名ウット、ドリエルなど、一般名ジフェンヒドラミン、医薬品名レスタミン)として生き残っています。
市販の点眼薬を使うと眠くなったり頭が茫したりすることがあるので、使用は控えましょう。では処方される点眼薬はどうでしょうか。パタノール(オロパタジン)、アレジオン(エピナスチン、3500円、3割負担で1050円)は、いずれも第二世代の抗ヒスタミン点眼薬ですが、防腐剤(塩化ベンザルコニウム、ソルビン酸カリウム)が含まれています。このような点眼を毎日使用していると、目の周りに色素沈着をきたしたり、赤くかぶれたりすることがあり注意が必要です。
もう一種類、市販されていない点眼薬としては、ステロイドがあります。代表薬はフルメトロン(150円、3割負担で45円)。ステロイドは長期に連用すると眼圧上昇や細菌感染のリスクがありますが、目が充血して痒い時(結膜炎)は、1日2?3回点眼すれば1日で治ります。結膜炎の状態では、パタノールやアレジオンをいくら使っても治りません。
話をまとめます。
花粉症の治療は第二世代抗ヒスタミン薬を服用し、目が充血したり目脂が出たりするときだけ、ステロイド点眼を1?2日使用することをお勧めします。ステロイドは毎日点眼することは控えます。目が乾いたらあくびをするようにして涙の分泌を促します。抗ヒスタミン薬を服用していれば、涙の中に微量ですが第二世代抗ヒスタミン薬の成分が含まれるので目薬の代わりになります。
コンタクトレンズ装着中に点眼してもよいかという質問をよく受けますが、点眼薬に含まれる防腐剤はその粒子が大きいため、レンズと角膜の間に入ると角膜を傷つけることがあるので、どんな種類のコンタクトレンズでも外した状態で点眼するのが理想です。コンタクトレンズ装着中に乾燥が気になる方は、ヒアルロン酸含有の点眼薬(ヒアレインミニ、防腐剤無添加、1個11.8円、1ヶ月分60個で自己負担424円)をおすすめします。
この季節は風も強いので、本当なら眼鏡をかければいいのでしょうが、マスクのせいでメガネが曇るのでいけませんね。やはり基本は目を乾かさないように、30分に一度ぐらいは仕事の手を休めて、伸びをしながらあくびををすることでしょうか。目薬を使う代わりに努めてあくびをしましょう。
書き忘れましたが、花粉症の治療で最も有効なのはステロイド点鼻薬(アラミスト)です。
以上です。
2022年の花粉飛散量は例年の1.2倍でやや多いようですが、皆さんマスクをきちんとつけているので、喉と鼻の症状は少なく、目の症状を強く感じるようです。
今回のテーマは、花粉症の点眼薬の使い方です。
市販の点眼薬を見てみると、アレルカット(第一三共 738円)、アルガード(ロート 1436円)、アルピタット(武田 938円)となっています。これらの点眼薬の主成分は、クロモグリク酸ナトリウム(インタール、医薬品登録中止、抗アレルギー薬、1972年発売)、クロルフェニラミンマレイン酸塩(ポララミン、抗ヒスタミン薬、1953年発売)です。
ポララミンは第一世代抗ヒスタミン薬と呼ばれ、私が研修医(1990年代初頭)の頃には「口渇、便秘、眠気の副作用に注意すること」と言われていました。1994年に眠気の少ない、いわゆる第二世代と呼ばれるアレジオンが発売されてからは、第一世代は医療機関ではほとんど使用されず、副作用の眠気を利用して、市販の睡眠薬(正しくは睡眠改善薬、商品名ウット、ドリエルなど、一般名ジフェンヒドラミン、医薬品名レスタミン)として生き残っています。
市販の点眼薬を使うと眠くなったり頭が茫したりすることがあるので、使用は控えましょう。では処方される点眼薬はどうでしょうか。パタノール(オロパタジン)、アレジオン(エピナスチン、3500円、3割負担で1050円)は、いずれも第二世代の抗ヒスタミン点眼薬ですが、防腐剤(塩化ベンザルコニウム、ソルビン酸カリウム)が含まれています。このような点眼を毎日使用していると、目の周りに色素沈着をきたしたり、赤くかぶれたりすることがあり注意が必要です。
もう一種類、市販されていない点眼薬としては、ステロイドがあります。代表薬はフルメトロン(150円、3割負担で45円)。ステロイドは長期に連用すると眼圧上昇や細菌感染のリスクがありますが、目が充血して痒い時(結膜炎)は、1日2?3回点眼すれば1日で治ります。結膜炎の状態では、パタノールやアレジオンをいくら使っても治りません。
話をまとめます。
花粉症の治療は第二世代抗ヒスタミン薬を服用し、目が充血したり目脂が出たりするときだけ、ステロイド点眼を1?2日使用することをお勧めします。ステロイドは毎日点眼することは控えます。目が乾いたらあくびをするようにして涙の分泌を促します。抗ヒスタミン薬を服用していれば、涙の中に微量ですが第二世代抗ヒスタミン薬の成分が含まれるので目薬の代わりになります。
コンタクトレンズ装着中に点眼してもよいかという質問をよく受けますが、点眼薬に含まれる防腐剤はその粒子が大きいため、レンズと角膜の間に入ると角膜を傷つけることがあるので、どんな種類のコンタクトレンズでも外した状態で点眼するのが理想です。コンタクトレンズ装着中に乾燥が気になる方は、ヒアルロン酸含有の点眼薬(ヒアレインミニ、防腐剤無添加、1個11.8円、1ヶ月分60個で自己負担424円)をおすすめします。
この季節は風も強いので、本当なら眼鏡をかければいいのでしょうが、マスクのせいでメガネが曇るのでいけませんね。やはり基本は目を乾かさないように、30分に一度ぐらいは仕事の手を休めて、伸びをしながらあくびををすることでしょうか。目薬を使う代わりに努めてあくびをしましょう。
書き忘れましたが、花粉症の治療で最も有効なのはステロイド点鼻薬(アラミスト)です。
以上です。
その34 ウイルス感染後症候群(post-viral syndrome)
オミクロン株が蔓延して、そろそろ皆さんの周辺でもかかる人が出てきていると思います。オミクロンはデルタ株までの新型ウルスとは異なり、上気道症状が中心で重症化しないと言われています。ところが、新型コロナ感染症は、初期の悪寒、発熱、咽頭痛などの症状以外に、長期的に悩まされる症状があり注意が必要です。
国立感染症研究所は①急性期症状、②急性期から遷延する症状、③回復後に出現する遅発症状、に分類しました。②は主に倦怠感、味覚・嗅覚障害、咳、呼吸困難などです。③はウイルス感染後疲労症候群とも呼ばれ、脱毛、集中力、記銘力低下、うつなどの症状です。脳に霧がかかったようになって、思考力や認知機能が低下するブレインフォグ(脳の霧)、頭痛、しびれなどの神経症状続きます(日本醫亊新報 No.5096 p6-7)。
海外でも米国疾患管理予防センター(CDC)英国国立医療技術評価機構(NICE)のガイドラインでは、COVID-19罹患後4週間以上続く症状をロングコビットと定義しています。
これは新型コロナウイルスに限った症状ではなく、インフルエンザ、コクサッキー(手足口病) 、パルボ(リンゴ病)、デング熱、伝染性単核球症などあらゆるウイルス感染症後にみられます。
前置きが長くなりましたが、今回のテーマはウイルス感染後症候群(post-viral syndrome)です。
1990年代に提唱された慢性疲労症候群という概念をご存知の方もあると思います。ウイルス感染後に意欲低下や全身倦怠感が続き、元気だった人が仕事もできずに寝たきりに近い状態になってしまいます。その原因がメンタルかフィジカルかが論争になったことがあります。最近では慢性的な免疫賦活状態(体の中で炎症がくすぶっている)ということがわかっています。
これと同様に新型コロナ感染症後に体内で炎症が続いた場合は、それに対応する治療が必要になりますので注意が必要です。頻度が高いものとして、
1) 二次感染としての化膿性咽頭炎、副鼻腔炎、肺炎、腸炎→抗菌薬による治療
2)長引く咳(無菌性の気管支炎)→ステロイドの吸入
3)意欲低下、思考力低下、易疲労感→食事療法、運動療法、向精神薬
これらの症状の原因は体内で炎症が遷延化していることにので、疲れが溜まり自律神経のバランスが低下(慢性の緊張状態)している場合に起こります。巷では新型コロナ後遺症外来が予約で一杯のようですが、症状に対する不安感が治りを悪くしている原因の一つだと考えられています。一番の治療は、自然に触れて、よく休む、よく笑うことでしょうか。
さて、もし皆さんが熱が出て近所の医療機関を受診しようにも「検査キットがない」「予約が一杯で受けられない」と言われた場合は、ご遠慮なくクリニックまでご連絡ください。テレワークならぬテレメディシンのシステムを用意しておりますのでぜひご利用ください。
https://www.sannoclinic.jp/online.htm
報道によれば英国も米国もオミクロンは減少に転じています。日本でも後1ヶ月もすれば収束するでしょうから、今年のお花見は思いっきり盛り上がれるといいですね。
以上です。
国立感染症研究所は①急性期症状、②急性期から遷延する症状、③回復後に出現する遅発症状、に分類しました。②は主に倦怠感、味覚・嗅覚障害、咳、呼吸困難などです。③はウイルス感染後疲労症候群とも呼ばれ、脱毛、集中力、記銘力低下、うつなどの症状です。脳に霧がかかったようになって、思考力や認知機能が低下するブレインフォグ(脳の霧)、頭痛、しびれなどの神経症状続きます(日本醫亊新報 No.5096 p6-7)。
海外でも米国疾患管理予防センター(CDC)英国国立医療技術評価機構(NICE)のガイドラインでは、COVID-19罹患後4週間以上続く症状をロングコビットと定義しています。
これは新型コロナウイルスに限った症状ではなく、インフルエンザ、コクサッキー(手足口病) 、パルボ(リンゴ病)、デング熱、伝染性単核球症などあらゆるウイルス感染症後にみられます。
前置きが長くなりましたが、今回のテーマはウイルス感染後症候群(post-viral syndrome)です。
1990年代に提唱された慢性疲労症候群という概念をご存知の方もあると思います。ウイルス感染後に意欲低下や全身倦怠感が続き、元気だった人が仕事もできずに寝たきりに近い状態になってしまいます。その原因がメンタルかフィジカルかが論争になったことがあります。最近では慢性的な免疫賦活状態(体の中で炎症がくすぶっている)ということがわかっています。
これと同様に新型コロナ感染症後に体内で炎症が続いた場合は、それに対応する治療が必要になりますので注意が必要です。頻度が高いものとして、
1) 二次感染としての化膿性咽頭炎、副鼻腔炎、肺炎、腸炎→抗菌薬による治療
2)長引く咳(無菌性の気管支炎)→ステロイドの吸入
3)意欲低下、思考力低下、易疲労感→食事療法、運動療法、向精神薬
これらの症状の原因は体内で炎症が遷延化していることにので、疲れが溜まり自律神経のバランスが低下(慢性の緊張状態)している場合に起こります。巷では新型コロナ後遺症外来が予約で一杯のようですが、症状に対する不安感が治りを悪くしている原因の一つだと考えられています。一番の治療は、自然に触れて、よく休む、よく笑うことでしょうか。
さて、もし皆さんが熱が出て近所の医療機関を受診しようにも「検査キットがない」「予約が一杯で受けられない」と言われた場合は、ご遠慮なくクリニックまでご連絡ください。テレワークならぬテレメディシンのシステムを用意しておりますのでぜひご利用ください。
https://www.sannoclinic.jp/online.htm
報道によれば英国も米国もオミクロンは減少に転じています。日本でも後1ヶ月もすれば収束するでしょうから、今年のお花見は思いっきり盛り上がれるといいですね。
以上です。
その33 健康診断(法定健診)後の面談
明けましておめでとうございます。宴会もやっていいのか悪いのか、もやもやした年末でした。大晦日のテレビでは、代々木公園での年越し参拝が超満員の様子が映し出され、今年一年の熱気が伝わってきます。お祈りの定番は、健康、家内安全、合格祈願などでしょうか。
今回のテーマは、健康診断(法定健診)後の面談についてです。
昨年、皆さんの健康診断結果を見直しました。対象は、産業医を担当している3社の計456人です。産業医として健康診断後に面談していただく方の基準は「要治療」の中で急を要する方や「要経過観察」で30代以下の方を考えています。
男性のワースト5は「肝酵素上昇」「高脂質異常」「肥満」「高血圧」「高尿酸血症」で、女性では「脂質異常」「肝酵素上昇」「貧血」「高血圧」「肥満」でした。異常の程度によって「要経過観察」または「要治療」と判定されます。「要治療」はもちろん医療機関を受診する必要がありますが「要経過観察」では受診されない方が多いと思います。
「要経過観察」の人こそ、医療機関を受診していただくようお勧めします。そして、血液検査で異常値を認めたときは、必ず2?3ヶ月後に再検査をするようにしてください。中には「一度受診して薬を出されたら、一生のまなければならない」とか「家で血圧を測るといつも正常だから大丈夫」などと、現実から目を背けて放っておく人がいます。そのような方は、毎年しつこく面談させていただきますw。
内科の診療は、薬を出すことだけではありません。最も大切なことは「健康への意識を高めること」です。「運動」「食事」「嗜好」を改善することが、服薬以上に重要です。我々臨床医は薬を処方するだけでなく、患者さんの生活習慣に焦点を当て、自己管理を促すことを心がけています。基本は、①毎日体重を測る、②カロリー控えめ、③飲酒、喫煙を控える、④股関節、肩関節ストレッチ、⑤息の上がる短時間の運動、です。
このような話をすると「忙しくて時間がなくて」「ストレスで食べてしまうんです」などとおっしゃる方もいらっしゃいます。確かにご自分の意思だけで食事・運動療法を継続することは、難しいものがあります。最近ではジムもトレーナーの指導を受けて行う、パーソナルトレーニングが人気です。月に数万円かかる場合が多いですが、トレーナーがいるといないとではやる気も変わってくると思います。
病院の診察代は初診料2,830円の3割(849円)です。気になる症状をインターネットでいろいろ調べる方がいますが、素人が調べると頓珍漢な情報ばかり拾ってきてしまいます。私も患者さんの症状についてインターネット検索をしますが、英文で調べるので情報量が多く、信頼できる順番に表示されます。皮膚所見を写真で撮影して、画像検索することもできます。いずれにせよ、得られた情報を吟味するための知識と経験が必要です。ぜひ、お気軽に病院を受診してください。
生活習慣を是正したにもかかわらず、半年かかっても検査値が正常範囲に戻らないときは、少量の薬を早めに始めた方がいいと思います。早めに服用することで、数値を正常範囲に戻すと、体内のシステムがうまく回り始め、体の疲れが溜まりにくくなります。生活習慣の改善によって薬物を中止できることもあります。
一方で、会社の健康診断(法定健診)を軽視しているわけではないと思いますが「自分は人間ドックを受けているからそちらの結果を見てからにする」とお考えの方もいらっしゃると思いますが、人間ドックは医療というよりはビジネスなので「過剰診断」「過剰治療」について留意する必要があります。人間ドックについては「健康一口メモその14(https://www.sannoclinic.jp/kenko.html#14)で解説していますので、ご参考ください。
最後に繰り返しますが、健康診断で「要治療」の人はもちろん「要経過観察」の人もぜひ医療機関を受診してみてください。
個別のご相談がある方は、人事部担当者に産業医面談希望とお伝えください。人事部を通さず、直接産業医宛にメールしていただいても構いません。個人情報は守秘し、事業者への報告が必要な時は、内容を加工して行います。
本年も健やかな1年を迎えられますよう、自己管理をよろしくお願いいたします。
以上です。
今回のテーマは、健康診断(法定健診)後の面談についてです。
昨年、皆さんの健康診断結果を見直しました。対象は、産業医を担当している3社の計456人です。産業医として健康診断後に面談していただく方の基準は「要治療」の中で急を要する方や「要経過観察」で30代以下の方を考えています。
男性のワースト5は「肝酵素上昇」「高脂質異常」「肥満」「高血圧」「高尿酸血症」で、女性では「脂質異常」「肝酵素上昇」「貧血」「高血圧」「肥満」でした。異常の程度によって「要経過観察」または「要治療」と判定されます。「要治療」はもちろん医療機関を受診する必要がありますが「要経過観察」では受診されない方が多いと思います。
「要経過観察」の人こそ、医療機関を受診していただくようお勧めします。そして、血液検査で異常値を認めたときは、必ず2?3ヶ月後に再検査をするようにしてください。中には「一度受診して薬を出されたら、一生のまなければならない」とか「家で血圧を測るといつも正常だから大丈夫」などと、現実から目を背けて放っておく人がいます。そのような方は、毎年しつこく面談させていただきますw。
内科の診療は、薬を出すことだけではありません。最も大切なことは「健康への意識を高めること」です。「運動」「食事」「嗜好」を改善することが、服薬以上に重要です。我々臨床医は薬を処方するだけでなく、患者さんの生活習慣に焦点を当て、自己管理を促すことを心がけています。基本は、①毎日体重を測る、②カロリー控えめ、③飲酒、喫煙を控える、④股関節、肩関節ストレッチ、⑤息の上がる短時間の運動、です。
このような話をすると「忙しくて時間がなくて」「ストレスで食べてしまうんです」などとおっしゃる方もいらっしゃいます。確かにご自分の意思だけで食事・運動療法を継続することは、難しいものがあります。最近ではジムもトレーナーの指導を受けて行う、パーソナルトレーニングが人気です。月に数万円かかる場合が多いですが、トレーナーがいるといないとではやる気も変わってくると思います。
病院の診察代は初診料2,830円の3割(849円)です。気になる症状をインターネットでいろいろ調べる方がいますが、素人が調べると頓珍漢な情報ばかり拾ってきてしまいます。私も患者さんの症状についてインターネット検索をしますが、英文で調べるので情報量が多く、信頼できる順番に表示されます。皮膚所見を写真で撮影して、画像検索することもできます。いずれにせよ、得られた情報を吟味するための知識と経験が必要です。ぜひ、お気軽に病院を受診してください。
生活習慣を是正したにもかかわらず、半年かかっても検査値が正常範囲に戻らないときは、少量の薬を早めに始めた方がいいと思います。早めに服用することで、数値を正常範囲に戻すと、体内のシステムがうまく回り始め、体の疲れが溜まりにくくなります。生活習慣の改善によって薬物を中止できることもあります。
一方で、会社の健康診断(法定健診)を軽視しているわけではないと思いますが「自分は人間ドックを受けているからそちらの結果を見てからにする」とお考えの方もいらっしゃると思いますが、人間ドックは医療というよりはビジネスなので「過剰診断」「過剰治療」について留意する必要があります。人間ドックについては「健康一口メモその14(https://www.sannoclinic.jp/kenko.html#14)で解説していますので、ご参考ください。
最後に繰り返しますが、健康診断で「要治療」の人はもちろん「要経過観察」の人もぜひ医療機関を受診してみてください。
個別のご相談がある方は、人事部担当者に産業医面談希望とお伝えください。人事部を通さず、直接産業医宛にメールしていただいても構いません。個人情報は守秘し、事業者への報告が必要な時は、内容を加工して行います。
本年も健やかな1年を迎えられますよう、自己管理をよろしくお願いいたします。
以上です。
その32 咳喘息について ー長引く咳に咳止めは効きませんー
空気が乾燥して寒くなってきました。マスクをつける習慣がついて、気道の乾燥は緩和されているかもしれません。この時期になるとコンコンと咳き込む人が多くなってきます。定義上、3週間以上続く咳を遷延性咳嗽(がいそう=咳の医学用語)といい、レントゲン検査や血液検査の適応となります。
一般に、咳を訴えて病院に行くと、咳き止めが処方され、1週間続くと抗菌薬が追加されます。それでも治らないとレントゲンや血液検査が行われて、肺炎でないことが確認されます。それらの検査で異常がない場合は咳喘息と診断されます。
咳喘息という病名を聞いた事がありますか?喘息の軽いバージョンのことです。喘息では気管支の炎症により、気道(空気の通り道)が狭くなり、呼吸をする時にピューピュー音がします。喘息の人は横になると重力の関係で、気道の腫れが強くなり余計に苦しくなるので、机に伏せる様にして休まなければなりません。
私が研修医だった30年前頃は、夜になると多くの喘息患者さんが発作を起こして、救急外来を受診する人が多く、入院になる人も少なくありませんでした。1978年にステロイドの吸入が国内で発売されましたが、その使用は重症患者のみに限定されていました。2009年の喘息治療ガイドライン(JGL2009)で初めて、ステロイド吸入が軽症喘息の第一選択薬に推奨される様になったのです。それ以降、喘息発作で病院を受診する人は激減しました。
ステロイドという薬は、副作用が強いイメージがあるせいか「ステロイドはちょっと抵抗があるので、咳止めをください」という方もたまにいらっしゃいます。全ての咳止めは麻酔作用がありますので、眠くなったり物の見え方がおかしくなったりするなどの副作用があります。咳止めは、気管支の炎症によって起こりやすくなった咳反射を、脳を抑制することで抑える非根本的な治療です。ですから「1ヶ月以上咳止めを飲み続けているけど咳が止まりません」という方はたまにいらっしゃいます。
一方吸入ステロイドも副作用があります。薬を吸い込んだ後、うがいをしないと口内炎ができたり、カンジダというカビが喉に生える場合があります。これらの副作用は、吸入をやめなくても、薬ですぐに治りますので心配ありません。吸入直後にうがいをすることで防げます。吸入薬の中にステロイドに気管支拡張薬(βブロッカー)が追加されている合剤があり、気管支拡張薬は動悸や手の震えの副作用があります。咳喘息であればステロイド単剤で十分です(おすすめはアズマネックス)。
風邪を引くと咳が残るという人は、咳喘息の症状が疑われます。ぜひ呼吸器専門の病院で相談してみてください。特に花粉症が強い方、蕁麻疹がある方、小児喘息の既往がある方は要注意です。
以上です。
一般に、咳を訴えて病院に行くと、咳き止めが処方され、1週間続くと抗菌薬が追加されます。それでも治らないとレントゲンや血液検査が行われて、肺炎でないことが確認されます。それらの検査で異常がない場合は咳喘息と診断されます。
咳喘息という病名を聞いた事がありますか?喘息の軽いバージョンのことです。喘息では気管支の炎症により、気道(空気の通り道)が狭くなり、呼吸をする時にピューピュー音がします。喘息の人は横になると重力の関係で、気道の腫れが強くなり余計に苦しくなるので、机に伏せる様にして休まなければなりません。
私が研修医だった30年前頃は、夜になると多くの喘息患者さんが発作を起こして、救急外来を受診する人が多く、入院になる人も少なくありませんでした。1978年にステロイドの吸入が国内で発売されましたが、その使用は重症患者のみに限定されていました。2009年の喘息治療ガイドライン(JGL2009)で初めて、ステロイド吸入が軽症喘息の第一選択薬に推奨される様になったのです。それ以降、喘息発作で病院を受診する人は激減しました。
ステロイドという薬は、副作用が強いイメージがあるせいか「ステロイドはちょっと抵抗があるので、咳止めをください」という方もたまにいらっしゃいます。全ての咳止めは麻酔作用がありますので、眠くなったり物の見え方がおかしくなったりするなどの副作用があります。咳止めは、気管支の炎症によって起こりやすくなった咳反射を、脳を抑制することで抑える非根本的な治療です。ですから「1ヶ月以上咳止めを飲み続けているけど咳が止まりません」という方はたまにいらっしゃいます。
一方吸入ステロイドも副作用があります。薬を吸い込んだ後、うがいをしないと口内炎ができたり、カンジダというカビが喉に生える場合があります。これらの副作用は、吸入をやめなくても、薬ですぐに治りますので心配ありません。吸入直後にうがいをすることで防げます。吸入薬の中にステロイドに気管支拡張薬(βブロッカー)が追加されている合剤があり、気管支拡張薬は動悸や手の震えの副作用があります。咳喘息であればステロイド単剤で十分です(おすすめはアズマネックス)。
風邪を引くと咳が残るという人は、咳喘息の症状が疑われます。ぜひ呼吸器専門の病院で相談してみてください。特に花粉症が強い方、蕁麻疹がある方、小児喘息の既往がある方は要注意です。
以上です。